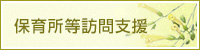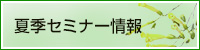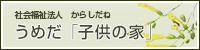「療育」と「支援」について
2025年08月5日
今回、東京都自閉症協会の機関誌「Prism」1)に、「療育」と「支援」について説明する機会をいただきました。せっかくの機会でしたので、その内容を共有させていただきます。
この言葉を日本に紹介し、肢体不自由の父と呼ばれた高木憲次先生2)は、「療育とは、現代の科学を総動員して不自由な肢体を出来るだけ克服し、それによって幸にも恢復したら『肢体の復活能力』そのものを(残存能力ではない)出来る丈有効に活用させ、以て自活の途の立つように育成することである。」と述べています。この中で注目するのは「時代の科学を総動員する」、つまり、今では当たり前と考えられるチームアプローチの実践の重要性が示されている点です。およそ100年前にこれが提示されたことに、ただただ感動します。一方で、現在では「障害の克服」というとらえ方は馴染まないでしょう。時代とともに変化した部分かと思います。そういったこともあり、現在では、「療育」から発展的に展開して「発達支援」という考え方が主流になっています3)。
「療育」においても「発達支援」においても、共通して重要なことは、本人の可能性や成長を保障することです。それは発達検査でとらえられるような数値が向上することだけを意味するわけではなく、本人が心身ともに健康で有意義な人生を送ることができるようになることを目指していると、私は理解しています。
チームアプローチにより、その子の持つ得意なことや、特徴などを把握することが重要な取り組みです。具体的には、本人が理解しやすい話し方はどういう方法か、本人がわかりやすいと思える方法のためにどんな工夫ができるのか、または、本人の辛さの背景には何があるのか、本人が拒む理由はどこにあるのか、などを理解しようと努める試みです。
方法を駆使し、環境を整え、関わりを整理し、期待したいことは本人の成長です。本人の成長とは単にできないことをできるようにさせることでもなく、検査で得られる数値が向上することだけではありません。一人の人として充実した人生が送れるようになることではないかと考えています。チームの中には親御さん等も含まれます。一緒に、この子を理解し、育ちを共有したいと思います。
学年が進み大きくなってきた子どもたちにとって、さらに重要になるのは、社会的なさまざまな経験です。同年代の仲間と過ごす時間や、共に取り組む経験であり、その中には余暇活動的な内容も含まれるでしょう。今どきの言葉では「推し活」も含まれることでしょう。
発達支援の現場では、家庭や学校だけでは経験することができない、それらの経験を提供し、子どもの育ちと成長を支援する場だと言えます。彼らが有意義な人生を送ることができるようになることを願っています。
2)高木先生についての紹介は、こちらのページ等を参照ください。
3)児童発達支援ガイドライン等を参照
« 新しい給食展示台が仲間入りしました スイカ割りという思い出 »
<<一覧へ戻る